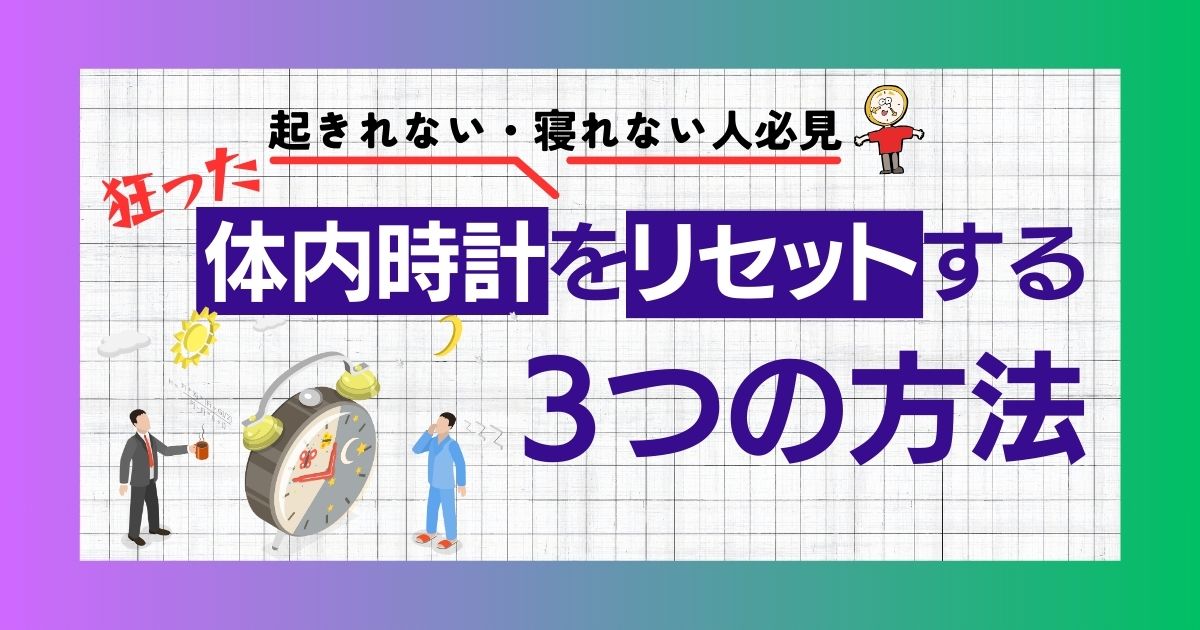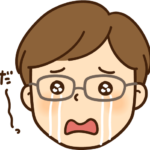 ケンイチ
ケンイチ毎日決まった時間に起きれない!
毎日決まった時間に寝れない!
睡眠サイクルがぐちゃぐちゃだ!
この記事を読むと、上記の悩みを解決できます。
人間には 「体内時計」が備わっており、自動的に日中はカラダと心が活動状態(ON)に、夜間は休息状態(OFF)に自動で切り替わる便利な機能を備えています。
しかし、時差ぼけ、休日の夜更かし、夏と冬の日照時間のズレ、夜勤と日勤を繰り返す交代勤務などをしてしまうことで、メラトニンレベルが低下し、体内時計を狂わせます。
このズレを修正できない日々が続くと、
狙った時間に寝られなくなったり、
起きることができなくなったり―。
その結果、慢性的な眠気や頭痛・倦怠感・食欲不振などの不調が現れてくるのです。また、深夜にならないと寝付けず昼頃まで起きられないという悪い睡眠パターンが固定化してしまうこともあります。
そこで今回は、以下の手順で体内時計の改善を提案します。
- 体内時計の仕組みをカンタンに知る
- 体内時計の解決策をあらゆる角度からレクチャー
- 具体例として私の体内時計を整えるルーティン紹介
この記事さえ読めば、あなたの体内時計は数日で元通りです。
体内時計とは、24時間の周期で働く自然なタイマー


体内時計とは、24時間の周期で働く自然なタイマーのようなものです。
このタイマーは、昼夜の変化に合わせて体の様々な機能を調整します。植物から昆虫、人間まで、地球上の生物ほぼ全てに存在しています。
この体内時計が影響を与える範囲は広く、ホルモンの分泌や心拍数、体温などがその一例です。
例えば、夜には体温が下がり、朝になると上がるのもこの体内時計の働きです。
そして、このタイマーは朝の日光によって毎日リセットされ、新しい一日が始まります。
しかし、この体内時計はちょっと不完全で、ちょうど24時間よりも少しだけ長い周期を持っています。
そのため、必然的に、日々少しずつズレが生じるので「修正」が必要です。
古い時計みたいなもんで、日を追うごとに時間がズレているイメージをもつとわかりやすいでしょう。
この時間のズレが大きくなると、朝うまく起きられなくなったり、昼間に眠くなったり、慢性的な頭痛や疲れに悩まされるのです。
そこでここからは、体内時計を整えるために必要な「3つのリズム」について解説します。
体内時計のリセットには「3つのリズム」の足並みを揃えることが不可欠


私たちの体は、朝起きて、夜眠くなるようにできています。それが体内時計です。
実は、体内時計というのは3つのリズムが存在します。
- メラトニンのリズム
- 腹時計のリズム
- 深部体温のリズム
体内時計をきっちり合わせるためには、この3つのリズムを調和させることが不可欠です。
これら3つのリズムが揃えば、狙った時間に眠くなり、狙った時間にシャキッと起きることが可能です。逆にどれか1つでもダメダメだと、体内時計がきっちり合うことはありません。(全部ダメダメよりはマシですけどね!)
①メラトニンのリズムを整える


メラトニンは、私たちが備える「神経伝達物質の一種」です。
メラトニンは俗に”眠気物質”とも呼ばれており、体内にメラトニンの量が増えると自然と眠くなる作用があります。
メラトニンの大きな特徴として、日中に光を浴びると減少し、夕暮れ時になると再び増加するという特性があります。ただし、メラトニンの減少は、夜にいじるスマホやPCのブルーライトでも起こるので注意が必要です。
ここで重要なのは、「日中にいかにメラトニンの活動を抑えて、夜にメラトニンを分泌させるか」です。
ここからは、この2点に着目して具体的な対策方法を考えていきます。
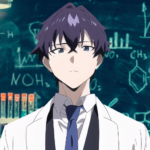
メラトニンの働きがあるから、昼は活動的に過ごせて夜は眠くなるわけだ。
起きたら日光を浴びる
まずは「毎朝決まった時間に起きて日光を浴びる」ことを習慣にしましょう。
朝にメラトニンの活動をしっかり押さえてあげることで、朝は目覚めやすくなり、夜には自然と眠くなる体質が出来上がります。
その理由は、起床して日光を浴びた約15時間後(就寝予定時間の約1~2時間前)からメラトニンがどんどん分泌して、眠気を誘発するという体の仕組みがあるからです。
なので、もし休日に二度寝したい人は、1回起きたときに頑張って朝日を5分ほど浴びましょう。この方法ならメラトニンリズムが崩れないので夜の睡眠に影響がでません。
夜のブルーライトをカットする
スマホやPCから発生する「ブルーライト」は波長が短く、エネルギーが高い光です。
脳はブルーライトを自然の昼光と誤解し、メラトニン(睡眠ホルモン)の生成が抑制される可能性があります。なので、少なくとも寝る1~2時間前にはブルーライトをカットすることが重要です。
このメカニズムは、数万年前の石器時代から変わっていません。夜の電気のない真っ暗なタイミングで体はメラトニンを大量に分泌するようになっています。現代における「夜も明るい状態」というのは、体にとっては不自然なのです。
なので、夜のブルーライトをできるだけカットする方法を模索することが解決の糸口です。そこで私が提案する方法は以下の5つになります。
- 目を保護するサプリを飲む
- ブルーライトをカットするメガネをかける
- 寝る2時間前にすべての電子機器の利用をやめる
- スマホやタブレットのライトの設定を暖色モードにする
- スクリーンデバイスにブルーライトカットフィルターを貼る
上記の具体的な対策方法についてまとめた記事があるので、よろしければそちらをご覧ください。


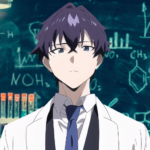
もしかしたら、これから数万年経てば光に対応できる進化するかもしれない。でも、今はまだ夜の光は生体にとって邪魔者でしかない。だから上手く付き合っていく必要があるのだ。
メラトニンサプリを飲む
メラトニンは、先ほどから申し上げているとおり、眠気を誘発するホルモンです。私たちの体の中で作られます。そのメラトニンが不足すると、眠りの質が低下したり、逆に起きられなくなることもあります。
とはいえ、夜のブルーライトは避けられないという人は多いでしょう。
ここでメラトニンサプリを寝る30分〜1時間前に摂ることで、体内に眠気ホルモンが十分に満たされて眠くなります。
メラトニンサプリは、私がいつも利用している「NOW Foods メラトニン 3mg」をおすすめします。これがあれば「寝れなくて困った!」という悩みが激減するはずです。
メラトニンは摂りすぎも危険でして、1回量のMAXが10mgと扱い方には注意が必要なサプリです。なので安全を考慮して多くても2粒を限界値に設定して試してみてください。サプリが効きやすい人なら初日から1粒でスッと眠れますよ。
なお、この記事では割愛していますが、体内時計を整えるサプリとしてビタミンD3も挙げられます。メラトニンとビタミンD3についての詳しい内容は以下の記事をお読みいただければ幸いです。


慢性ストレスをセルフケアで減らす
さっきからメラトニンの話ばかりしてきましたが、目覚めたときに大活躍するのが、メラトニンと同じ神経伝達物質である「コルチゾール」というストレスホルモンです。
わかりやすく説明するとこんな感じ。
メラトニンは眠気をつかさどるホルモン。夜に出るといい。
コルチゾールは覚醒をつかさどるホルモン。朝に出るといい。
コルチゾールは私たちが寝起きから活動的になるために必須な成分です。
体に「そろそろ動けよ」という合図と、それに必要なパワーを送ってくれます。つまりコルチゾールもメラトニンと同様になくてはならない神経伝達物質なのです。
しかし、ストレスが高まると、この2つのバランスが狂ってしまいます。
ストレスがかかると、体は「戦うか逃げるか」の状態になり、コルチゾールが多く生成されます。コルチゾールが強い状態だと、メラトニンがうまく分泌されず、眠れなくなるのです。
研究者によると、慢性的なストレス状態では、メラトニンの生成を阻害するホルモンが働きます。結果、夜になってもなかなか眠れず、次の日に影響が出ることが多いです。
対策としては、ストレスを減らす活動が有効です。例えば、ヨガや瞑想、お風呂に入るといった心地よいセルフケア習慣を持つことで、コルチゾールを抑え、自然な概日リズムを取り戻せる可能性が高まります。
この方法は過去の記事でまとめましたので参考にしていただければ幸いです。


②腹時計のリズム


ある実験を紹介します。
ラットの体内時計を壊したところ、睡眠のリズムや体温のリズムなど、生命活動のリズムが消えてしまいました。
ところが、体内時計が壊れたラットに毎日決まった時刻に餌を与え続けると、その時刻の前後の活動量が増えたのです。
そして、そのエサを与えた時間から約12時間後に活動量が最も低下する(休息する)という、正しいリズムが現れることもわかりました。
つまり、腹時計のリズムでも体内時計と似たリズムを作ることができるというわけです。なお、食事の量が多いほど、時計の針を合わせる力は強くなります。
朝ごはんをたべる
前述した内容から、「朝起きたら朝食をとる」ことが体内時計の時刻合わせになります。
この際は、理想の時間に朝食を摂ることです。そうすると夜の体内時計が合いやすくなります。
逆に、食べる時間を変則的にしたり、寝る直前に食事をすると、体内時計がたちまち狂うので気を付けてください。
そもそも、寝る直前に食事をすると、寝ている間に食べたものを消化したり吸収したりすることにエネルギーを使ってしまいます。すると、良質な深い睡眠に入るヒマがありません。
そういった意味でも、寝る2~3時間前までには食事を終わらせておくほうが無難です。
③深部体温のリズム
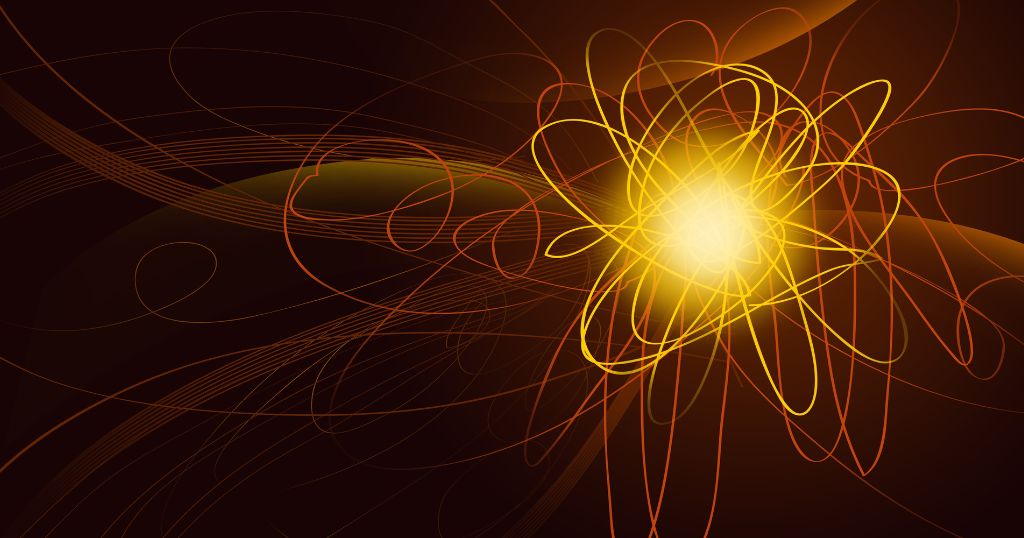
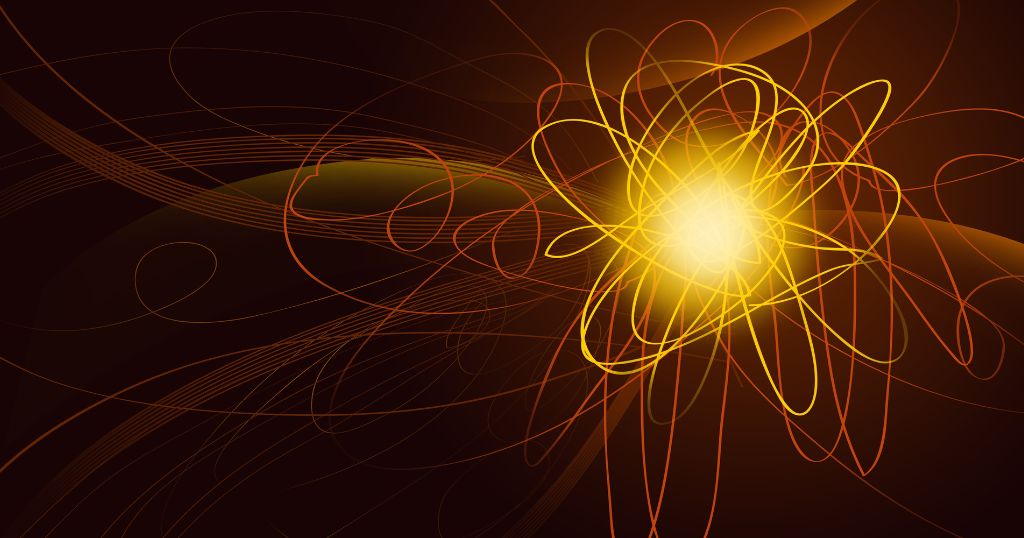
深部体温のリズムは、文字どおり体の内部(直腸)の温度が変化するリズムを指します。
深部体温には、以下のような特徴があります。
- 起床から11時間前後に最も高く、22時間前後に最も低くなる
- 深部体温が高い場合には体が活発になる
- 深部体温が低い場合には眠くなる
- 深部体温の上げ下げの落差が大きいほど睡眠の質が上がる
これだけ聞いてもよくわからないですよね。では、実際に深部体温を利用して体内時計をコントロールする方法を具体的に解説します。
もっとも深部体温が高いタイミングに運動する
もっとも深部体温が高いタイミング(起床11時間前後)までに思いっきり運動をしてさらに深部体温を上げておきましょう。
そうすることで、「深部体温が高いタイミングで運動→運動によるさらなる体温上昇→深部体温の落差→深部体温がいっきに下がって自然に眠くなる」という流れが上手くいきます。
例えば、「朝7時に起きたなら、18時から運動する」、「朝10時に起きたなら、21時に運動する」といった具合です。
これらのタイミングで体を動かせば体温を効果的に上げることができます。
反対に、睡眠時間に近くなるにつれて、深部体温を上げないように活動レベルを低くしてあげることも重要です。難しいことはありません。運動が終わった後はゆっくりすればいいのです。
寝る2時間前にお風呂に入る
夜は入浴せず、シャワーだけで済ませる人もいるかもしれません。しかし、シャワーだけでは体全体が温まらないため、深部体温が下がりにくく、入眠しにくいです。
なので、湯船に浸かることをルーティンに入れてみてはいかがでしょうか。
お風呂に入ることで深部体温がいっきに上がります。その反動で、体内にこもった熱を手足から放出するために深部体温が下がり、眠くなるのです。
入浴時間は、38℃~40℃くらいのぬるめの温度で入浴した場合は、1時間ほど前でも十分です。40~42℃のあつめの温度なら2時間前に済ませておくほうがいいでしょう。
それでも朝が苦手なら自分の睡眠タイプを確認しよう!


それでも朝が苦手なら、睡眠に関する権威「ブレウス博士」が提唱した「睡眠クロノタイプ診断」を実践してみてはいかがでしょうか。
「睡眠クロノタイプ診断」とは、「1日の中で最も活動的で集中力が高まる時間」は人それぞれ違い、それを知ることによって自分の活動スタイルを決定する方法です。
例えば、本来は夜型の人が無理に朝活しようとすると、体の内部時計、すなわち概日リズムが狂ってしまい、質の良い睡眠が得られません。ちなみに私は夜型「オオカミタイプ」と診断されて、そのように振る舞うことで生活リズムが逆に整った気がしています。
こちらを詳しく知るには以下の記事をご覧ください。


私の場合:体内時計を整えるためのルーティン


私の場合で恐縮ですが、本日紹介した体内時計を整える方法を実践した1日のスケジュール例をご紹介します。このスケジュールは、ご自身の生活スタイルに合わせて自由にアレンジしてください。
カーテンを開けた日当たりのいい窓越しに歯磨きをしながら5分ほど過ごす。これで体内のメラトニンが減少し、元気が出る。この効果は夜にも影響するため、しっかり朝日を浴びる。そのあとに軽めの朝ごはんをたべて、腹時計を起動。
この時間帯は体内時計に影響しない。このタイミングでカフェインの摂取をしておく。カフェインは体内に長時間(4~16時間)留まり、睡眠に影響を与えるから。
がっつり運動する。基本はHIIT30分。夜の食事も21時頃に済ませておく。
22時頃に30分ほどゆっくり湯舟に浸かる。そして、0時以降のブルーライトの利用を抑えつつ、1日のストレスを癒すセルフケアを行う。1時頃にメラトニンサプリを飲み、ベッドにつき、暗い証明で本を読んで寝落ちする。
おわりに:体内時計を整えればシャキッと起きれる人になる!


体内時計を整えることは、日常生活の質を向上させるためには避けては通れません。
体内時計をコントロールできれば、朝の目覚めがこれまでにないほどスムーズになり、1日を通してエネルギーレベルも高い状態でキープできます。
ここまで話してきたように、メラトニンのリズムを調整したり、食事のタイミングを気にしたり、深部体温のリズムに合わせて運動や入浴を計画することで、体内時計はしっかりとリセットできます。
それでも朝が苦手なら、自分自身の睡眠タイプを理解しましょう。そのうえで本日紹介した方法を試すのです。それによって、更にパーソナライズされた対策が可能となります。
自分の体内時計に合わせた生活を送ることで、シャキッと起きて、一日を有意義に過ごせる人になれるのです。部分的でも良いので1つずつ改善して、朝はスッキリ目覚め、夜はあっという間になられるような毎日を目指しましょう!