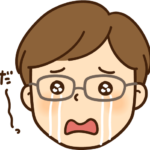 ケンイチ
ケンイチ積極的に食べた方がいい「体に良い食材」や、逆になるべく食べない方がいい「体に悪い食材」を教えてほしい。
この記事を読むと、上記の疑問や悩みを解決できます。
食事は人間の健康に大きく関わっていることは、皆さんご存じなはずです。
それにも関わらず、なぜか太る体。なぜか起きる不調。なぜかいつも頭がボーっとしている…。
これらの症状は、実にさまざまな原因が考えられます。しかし、食事が原因である可能性が高いことには、意外にも気づいていない方(目を背けている方)が多いことが現実としてあります。
あるときに、私も「その一人」であることに気付き、あらゆる健康関連書籍を読み漁り、どうやら食事まわりを改善することが大優先であることがわかりました。
そこでこの記事では、はじめに「健康的な調理法」をサクッとレクチャーした後に、具体的な「体にいい食品と体に悪い食品」にスポットを当てて解説していきます。
この記事を読むことで、体に良い食材を取り入れて健康体になり、体に悪い食材を避けてリスクを減らせます。
健康的な調理法


良い食材を知る前に、「健康的な調理法」について知っておきましょう。なぜなら、いくら良い食材を使おうと、調理法が悪ければ本末転倒だからです。
つまり、調理法も食品と同じように「良い調理法」と「悪い調理法」があるということ。
では、さっそく健康順に並べたものをご覧ください。
- 生
- 蒸す
- 茹でる
- 焼く
- 揚げる
生で食べるのが一番健康的で、揚げるのが一番サイアク。
これを頭に入れておくだけで、鶏料理を作るときでも「今日は、からあげはやめて、鶏を蒸してでサラダを作ってみるか」という発想も浮かんできます。
本日紹介する健康食材たちも、このような「良い調理法」を知った上で見てみると、より良い発想が生まれてくるでしょう。
体に悪い食事のデメリット|体に良い食事のメリット


体に悪い食事のデメリットは以下のとおり。
- 太る
- 老ける
- 活力が下がる
- 脳機能が落ちる
- 体調が悪くなる
- 幸福度が下がる
- やる気がなくなる
- メンタルが弱くなる
- 病気のリスクが上がる
逆に、これから食事について真摯に学び、「体に良い食事」を実践することで、私たちは上記に挙げたデメリットと正反対のメリットを得ることができます。
- 痩せる
- 若返る
- 活力に満ち溢れる
- 脳機能がフル回転
- 体調が良くなる
- 幸福度が上がる
- やる気が上がる
- メンタルが強くなる
- 病気のリスクが下がる
どうでしょう。
ちなみに、「マズイものを我慢して食べろ」と言っているわけではないのでご安心ください。
つまり、「美味しいけど不健康な食材を選ぶ割合を減らして」→「美味しくて健康的な食材を選ぶ割合を増やそう」ということです。
こういわれると、「じゃあできる、、、かも!?」とちょっぴり思えませんか?
そんな希望を胸に秘めつつ、ここからいよいよ「体に良い食品」と「体に悪い食品」を一気に紹介していきます!
体に良い食品「毎日摂るべき」


まずは体に良い食品を見ていきましょう。
「体に良い食品」というくらいですから、摂るべき頻度は多めです。
ただし、何でも偏りはよくありません。体に良いからといって極端に取りすぎてしまうとかえって健康を害すのが食事の難しいところ。モノによっては目安量も提示していますので、参考にしてみてください。
「体に良い食品」に切り替えたとき、あなたはこれまで感じたことのない大量のエネルギーと回復力が引き出されるでしょう。ちなみに、それを実感するには2~6か月はかかります。
全粒穀物


| 食べる推奨頻度 | 毎日? |
| おすすめ食材 | 玄米 |
食物繊維やビタミン、ミネラルなど健康に有用な成分を豊富に含む全粒穀物は、様々な病気の予防に役立つ可能性があります。GI値が低いため、白米と比べて圧倒的に血糖値の上昇が緩やかです。
- 玄米
- 全粒粉のパン
- オートミール
上記の食品でいくと、「全粒粉のパン」は日本ではなかなか手に入らないこと、「オートミール」はご飯として食べるには一般的ではないことから、「玄米」が主食の筆頭格になるでしょう。
ただし、玄米などの穀物の否定的な意見として、「玄米には、フィチン酸と呼ばれる成分の強力な”排出作用”が人体に少なからずの悪影響を与える」というものがあります。
でも安心してください。
玄米に含まれるフィチン酸濃度を下げることもできます。
それが「発酵玄米」という方法です。
作り方もとってもカンタン。
「水に数日浸しておくだけ」。詳しい方法は以下のリンクから調べてみてください。
また、玄米などの穀物の表皮には残留農薬のリスクがあるので、「無農薬」のものを選ぶと良いでしょう。
フィチン酸にしろ、残留農薬にしろ、食べ過ぎなければ体内にはほとんど影響がないレベルだという見解も多いです。ミネラルの排出に関しても、サプリで補ったり麦茶を飲んだりしていればさらにリスクは下げられます。
結局、自分の体の状態を見ながら調節していく方法がベターということですね。
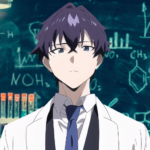
私は三合を発酵玄米にして、一週間かけて食べている!すぐに食べないものは出来立ての状態で冷凍してしまおう!
表皮が残っているぶん、消化はしにくくなっているため、消化力の弱い人は少し注意が必要です。例えば、「玄米を食べると必ずお腹が張る」という方は合わない可能性があります。これは、「品質による副作用」なのか、「玄米を食べたことによる副作用」なのか、見極めていきましょう。
野菜


| 食べる推奨頻度 | 毎日 |
| おすすめ食材 | ✓アブラナ科 ✓緑黄色野菜 |
野菜は健康に良い食品なので、毎日積極的に食べることを意識しましょう。できればオーガニック推奨ですが、そうでなくてもOK。(摂らないより全然マシ)
そして、野菜のなかでも特に体に良いとされているのが「アブラナ科と緑黄色野菜」です。
大根
白菜
水菜
ちんげん菜
ブロッコリー etc…
さらに!!!
この中でランキングを付けるなら、圧倒的1位の野菜は「ブロッコリー」です。
ブロッコリーは栄養価が物凄く高く「タンパク質・鉄分・マグネシウム・ビタミンC・ビタミンA・葉酸・カルシウム・食物繊維・ポリフェノール」などが豊富に含まれています。ちなみに、2位は同率。「小松菜」と「ほうれん草」です。
野菜にこだわりがない方であれば、「ブロッコリー・小松菜・ほうれん草」は定期的に食べましょう。
アボカドは正確には果物ですが、ここで紹介させてください。
アボカドは「最も栄養価の高い果物」として、ギネスブックに登録されているスーパーフードです。良質な脂質をはじめ、豊富な食物繊維、ビタミン、カリウムが含まれています。こちらも積極的にとっていきましょう。
果物


| 食べる推奨頻度 | 1日握りこぶし一個分 |
| おすすめ食材 | ✓いちご ✓ブルーベリー |
果物は、抗酸化作用が高く、美容にもいいので、おやつ代わりとして取り入れていきましょう。
基本的には好きな果物で構いませんが、健康という面を考えるならば、以下の「栄養価の低い果物」を避けつつ、「栄養価の高い果物」を取り入れる習慣を持ってみるといいかもしれません。
- 柿
- スイカ
- いちご
- ぶどう
- リンゴ
- みかん
- デコポン
- キンカン
- ブルーベリー
注意点は、果物は糖質が多いので、チョコレート同様、食べ過ぎないこと。(1日握りこぶし一個分)
また、健康によさそうなフルーツジュースですが、成分が濃縮され、糖分過多になりやすいため、おすすめできません。(メリットよりもデメリットのほうが大きくなる)
また、「かゆくなる果物」はアレルギーなので、控えましょう。果物のアレルギーに関しては、以下の記事が参考になります。
私の場合は、最強のアンチエイジングフルーツともいわれている「ブルーベリー」を毎日食べています。ブルーベリーは冷凍のものでも問題ないそうなので、私はいつもこちらを購入しています。
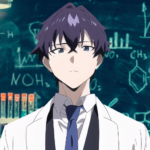
スーパーで売っているものは、酸っぱく、おいしいとは言い難いが、これはとても甘い。おまけに国産なので安心だ。
colum:果物の加工の方法によって悪玉コレステロール量が変わる?
2013年に、生のリンゴとリンゴジュースによって悪玉コレステロールがどれくらい増減するかという研究が行なわれました。
実験は、まず参加者を次の二つに分けます。
*毎日、生のリンゴを食べてもらうグループ
*毎日、リンゴジュースを飲んでもらうグループ
4 週間後にコレステロール値などを測ります。
その結果、次のことがわかりました。
*生のリンゴを食べたグループは、LDL( 悪玉)コレステロールが減少した
*リンゴジュースを飲んだグループは、LDLコレステロールが増加した
つまり、生の果物を食べると減るはずの悪玉コレステロールが、ジュースでは増えているのです。
原因は、二つあります。一つは、ジュースを飲みやすくするために、口当たりをよくするために、体にいいといわれているポリフェノールや食物繊維が取り除かれるからです。二つめは、さらにおいしく飲めるようにと、人間の脳を狂わせる果糖ブドウ糖液糖( 甘味料)といった糖質が大量に投入されることが多いからです。
果物はぜひ、生で摂る習慣をつくってみましょう。
colum:幸福度がアップするおやつ
野菜や果物をおやつとして食べると、 うつ病の症状が減り、幸福感はアップしてポジティブな気分が出やすくなります。その代表的なものは以下のとおり!
バナナ/リンゴ/オレンジ・レモン( 柑橘類)/ブルーベリー/ミックスベリー/キウイフルーツ/ニンジン/キュウリ/ブロッコリー/ナス/サツマイモ/ジャガイモ/カボチャ/セロリ/キャベツ/ トマト
今食べているおやつを果物や野菜にシフトするだけで、体にもメンタルにも効果があるなんて嬉しい限りですよね!
魚類


| 食べる推奨頻度 | 週3回以上(理想は5回以上) |
| おすすめ食材 | ✓青魚 |
魚介類全般、体に良いのですが、特に体にいい魚が「青魚」です。
- サバ
- ブリ
- イワシ
- サンマ
目標は「週5回以上」ですが、「週3回以上」でも合格ライン。
なお、缶詰でもいいそうです。ただし、缶詰を選ぶ際は「添加物・塩分・BPA(体に有害な化学物質)」が含まれていないものを選ぶようにしてください。
肉類


| 食べる推奨頻度 | 週2回 |
| おすすめ食材 | ✓鶏むね肉 ✓鶏ささみ肉 |
肉類のなかでも健康な順番があります。
- 1位 鶏肉
- 2位 豚肉
- 3位 牛肉
さらに健康を意識するなら、放牧(グラスフェッド)や平飼いで飼育された家畜。そして、ひれ肉などの脂身が少ない部位がおすすめです。
特に、グラスフェッドのお肉は、肉のデメリットやリスクを極端に減らしてくれるので、検討したいところ。あまり値段が張らない卵あたりから導入してみましょう。
豆類


| 食べる推奨頻度 | 毎日 |
| おすすめ食材 | ✓大豆製品 ⇒納豆 |
豆類のなかでも、積極的に取ってほしい食品が大豆製品です。
- 納豆
- 豆腐
そして、なかでも圧倒的に体に良い大豆製品が「納豆」です。
日本から生まれし最強食材の1つである納豆は、ビタミンKが豊富でビタミンD3サプリとの相性がかなり◎。週に3回以上は摂ってほしい食品の1つです。
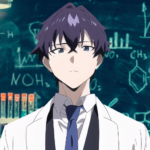
私はよく、納豆とキャベツとごま油と韓国のりをあえて、お酒のおつまみにしているぞ。
ナッツ類


| 食べる推奨頻度 | 毎日(25g) |
| おすすめ食材 | ✓無塩ローストのミックスナッツ |
食物繊維が豊富で良質な脂質が含まれており、非常に栄養価の高い食品です。
選ぶポイントは、以下のとおり。
- 無塩でローストされたナッツ
- いろんな種類のナッツを食べた方がいいのでミックスナッツ
量は、1日25g程度(手のひらに乗るくらい)食べるのが良いとされています。
今常備しているおやつを、ミックスナッツに置き換えられれば完璧です。
ただ、私の場合、飽きると半年くらい口にしたくない時期が三回来ました。そういうときは、思い切って「有塩」のナッツを購入しています。一番おすすめはコレです。クレイジーソルト最高!!!
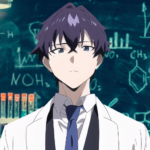
諦めてポテチを食うより100倍いい。
カカオ70%以上のチョコレート


| 食べる推奨頻度 | 一日4かけらまで |
| おすすめ食材 | ✓カカオ70%以上のチョコレート |
カカオやポリフェノールに健康効果があります。
ただし、カフェインや砂糖が含まれているので、食べ過ぎには注意です。量は一日4かけらを推奨。
個人的には、個包装タイプの「明治のチョコレート効果 カカオ72%」がおすすめです。
「1個包装あたり、2かけら入っているので、一日2個包装まで」と、制限が効きやすいです。ダースタイプだとついつい食べ過ぎちゃいますからね。
ちなみにレベルが高い人はコチラもおすすめ。
↑「カカオ95%」は食べ過ぎないだろうからダースタイプでOK。(笑)
チョコレートに関しても、ミックスナッツや果物と同様です。おやつの代替食品として上手く組み合わせていきましょう。
コーヒー


| 推奨量 | 1日上限4杯 |
| おすすめ食材 | ー |
コーヒーは一般的なコーヒーカップ4杯程度までにしましょう。マグカップであれば2杯程度ですね。カフェイン耐性を見極めながら飲むことがコツです。(体の不調などで判断)
カフェインは、惰性で摂ると依存しがちで、過剰摂取に繋がりかねません。「カフェイン休肝日」や「カフェイン上限を低く見積もる」などといった「自分ルール」を決めてコントロールしましょう。
それに加えて、熱すぎると、胃が荒れる原因になったり、食道がんのリスクが増したりするので、温度にも気を付けましょう。
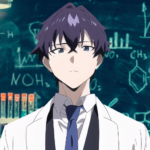
ちなみに熱帯原産のコーヒーの多くは「カビ」ている。なので、少量のカビ毒に被ばくすることになる。1杯2杯じゃ全く問題ないが、100杯、200杯と飲むうちに不調が起きる場合がある。
それを避けるために私は、無毒化100%アラビカコーヒーを飲んでいる。このコーヒーは、カビの毒素を除去するために、細心の注意を払って高地の1つの場所で栽培され、収穫され、慎重に処理されて出荷されているのだ。
多少値は張るがクリーンで爽やかな風味が朝を優雅にしてくれるぞ。
良質な油


| 食べる推奨頻度 | 大さじ4杯程度 |
| おすすめ食材 | ✓良質な油(特にオリーブオイル) |
オメガ3系とオメガ9系を摂って、オメガ6系を避けましょう。健康な順番は、「オメガ6系<オメガ9系<オメガ3系」です。
- あまに油
- えごま油
- 魚油(魚の脂質)等
基本的にオメガ3系は熱に弱いので、生で摂ることをおすすめします。最近のフライパンはノンオイルでもこべりつかずに焼けるものも多いので、焼いた後にお好みのオメガ3系の油をサラッと料理にまぶすといいでしょう。サラダであれば、小さじ一杯を直接かけて召し上がってください。
炒め物や揚げ物などの調理をするならオメガ9系のほうが向いています。オメガ6系は健康に良くないので特別な事情がない限りは使わないようにしましょう。
オメガ3系もオメガ9系も、以下の項目に該当するものを選ぶようにすると、必然的に質の高いものを入手できます。
- コールドプレス(低温圧搾法)
- 光を通さない容器に入っている
- エクストラバージンオイル(一番搾り)
上記の条件を全て満たしていて私自身が愛用しているのは「Gaea, ギリシャ、エキストラバージンオリーブオイル (500 ml)」です。
このオリーブオイルは、クレタ島産のもので、ギリシャのオリーブオイル生産量の半分を占めるといわれているほどの生産量を誇ります。ほかの地中海地域産のものと比較しても非常に高品質であることで知られています。
MCTオイル(中鎖脂肪酸)_肥満予防、炎症抑制など「いいことづくし」の魔法のオイル
中鎖脂肪酸と呼ばれる脂肪酸が非常に多く含まれている代表的な食品がMCTオイルです。
バイオハッカーのなかで非常に注目されているスーパーオイルで、私自身も、大さじ一杯をコーヒーに入れて欠かさず毎日摂取しています。
中鎖脂肪酸のざっくりとした効果は以下のとおり。
- 体の抗酸化を促進する
- 脳や筋肉を有効に働かせる
- ケトン体に入りやすくなる
- 肥満になりにくい体質にする
- 体内で速やかにエネルギーに変換される
この時点で凄さは伝わってるかと思います。
そのなかでも特におすすめなのが、MCTオイルのなかでも「C8」と呼ばれるタイプです。
一般的なMCTオイルは「カプリル酸(C8):C10(カプリン酸)=6:4」で生成されています。
そのなかでもC8のみで生成されたオイルは別格です。一般的なMCTオイルに⽐べ消化・吸収が速く、また効率的にケトン体を産生し、速やかに脳や筋⾁のエネルギーとなります。
先ほど挙げたメリットをより感じやすいのがC8タイプだということです。
私が愛用しているのはコチラ
これは、私が尊敬している最強のバイオハッカーと名高いデイヴアスプリー氏の会社で製造しているこだわりの商品です。成分も安心、効果も優れています。他のC8オイルも使用したことがありますが、こちらのほうが質が高いように感じます。
海藻類


| 食べる推奨頻度 | 週3回以上 |
| おすすめ食材 | ✓わかめ |
海藻類は、栄養価が高く、水溶性食物繊維が豊富です。
ところで、日本人は海藻を消化できる人が多いけど、海外の人は消化できない人の方が多いことはご存じでしたか?
これは、日本が島国に属していて、長き食文化で培われたものだと考えられます。つまり海藻は、日本人にとって、かなり相性の良い食材ということです。
海藻であれば、特に決まりはありませんが、日常的に取り入れやすいのは「わかめ」になります。味噌汁に入れてもいいし、刺身にして食べても美味しいといったように、わりと汎用性が高い食べ物です。
特に味噌汁は、発酵食品としても健康レベルの高い食品なので、積極的に一緒に摂りたいところです。
卵


| 食べる推奨頻度 | 毎日1個 |
| おすすめ食材 | ✓生卵 ✓温泉卵 ✓ゆで卵 |
卵は栄養価が高いので、毎日一個は食べたいところです。
食べ過ぎはよくないよいうですが、ある本の情報によると「卵は貴重なたんぱく源。1日5個までなら大丈夫」と謳っているものもあるくらいなので、あまり神経質になる必要はない、”安全食品”だと考えられます。
良質な動物性脂肪
動物性脂肪は、太るだとか、コレステロールを増やして血管の病気になりやすくなるなんて言われています。ですが、これはもはや時代遅れの考えです。
「質の良い」動物性脂肪を摂ることができれば、デメリットよりも圧倒的に大きいメリットを受け取ることができます。
それを知るためには「質が悪い」動物性脂肪の特徴を知ることが必要です。
- ホルモン剤や抗生物質を使用している食肉
- 遺伝子組み換え飼料を与えられている食肉
- 化学調味料や保存料などの添加物のリスクが高い加工肉
スーパーで安く売られている肉のほとんどは上記に該当します。
「質の良い」動物性脂肪は、「なるべく自然な環境」で、「自然なものを食べて育った動物の肉」であることが条件です。
どれもスーパーの肉と比べれば割高(1.5倍~)ですが、健康の高みを目指すなら妥当な投資といえます。
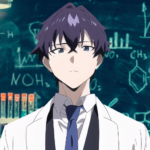
とはいえ、最近はスーパーでもなかなか良いお肉が売られるようになっている。肉の素材の味を楽しむような料理だけグラスフェッドビーフを使うなど、家計を圧迫しない程度にバランスよく召し上がるといいだろう。
ちなみに私の場合は、ステーキをミディアムレアで食べたいときに「ミートガイ」という通販サイトでグラスフェッドビーフを購入している。コスパも味も抜群だ。
体に悪い食品「積極的に避けるべき」


ここではあえて一つずつ言及しなくてもわかるでしょうから、サクッと紹介します!
基本的に、これから紹介する「体に悪い食品」は添加物が問題です。添加物は非常にさまざまありますが、以下のようなものが代表的です。
- スクラロース
甘味料。ジュースやお菓子ほか多数に添加。毒性があり、免疫力を低下させる。
- アセスルファムK
甘味料。ジュースやお菓子ほか多数に添加。ラットへの大量摂取で死亡例あり。特に授乳中は避けたほうが良い。
- 調味料(アミノ酸等)
あらゆる食品に添加。動悸、めまい、だるさ、神経系への影響、発ガン性も指摘されている。
- 亜硝酸Na
発色剤。コンビニのおにぎりなどに添加。ほかの物質と結びつき、発ガン性物質に変化。
- ソルビン酸K
保存料。菓子パンなどに添加。細胞の遺伝子を突然変異させる。
- 次亜塩素酸Na
殺菌料、漂白料。カット野菜や弁当などに添加されている。腹痛、吐き気、嘔吐、下痢を引き起こす可能性がある。
この辺の添加物についてもっと詳しく知りたい方は以下の記事をどうぞ。
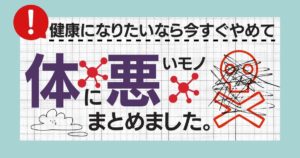
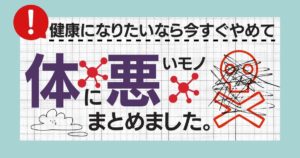
砂糖が大量に含まれている食品(お菓子やジュースなど)


もうここで改める必要はありませんね。お菓子は明らかな「糖質過多+添加物過多」で、もはややりたい放題。栄養成分はほぼないっくせにお腹いっぱいにしてくれないので、必ず食べ過ぎます。
白砂糖は、原料であるサトウキビに含まれる「ショ糖」という甘み成分を、ほぼ純度100%に調整した砂糖です。 ショ糖がほぼ100%というのは、 白砂糖をとると血糖値が急上昇することを意味します。
血糖値が上がると、すい臓からインスリンというホルモンが分泌されます。
インスリンは血中の糖が各臓器にとり込まれるように作用し、結果的に血糖値を下げるのですが、血糖値が急上昇したことでインスリンが大量に分泌されると、血糖値が急激に下がります。
すると体がダルくなるほか、脳の神経伝達物質が乱れ、抑うつ状態になる、イライラして攻撃的になります。一見すると「精神的な障害」と見える症状が起こりやすくなるといいます。また、血糖値の急上昇と急降下は、空腹感を増大させます。
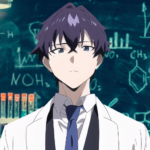
ご飯を食べてすぐ気絶するように寝てしまう人は要注意。それはインスリンが大量に分泌されているサインかもしれない。
それだけではありません。
血中で余った糖は、血中のタンパク質と結びついて「AGEs」という有害物質に姿を変え、体中の細胞にとりついて機能不全に陥らせます。これを「糖化」といいますが、俗に細胞の「コゲ」と呼ばれています。
糖化は酸化と並んで病気や老化の最大要因とされています。(がんや糖尿病の温床)
いつまでも健康でいたいのであれば、「甘いもの=たまに食べるご褒美」という立ち位置に変更した方が良さそうです。
砂糖のほかに注意すべき甘味料は以下。
・メープルシロップ
・黒砂糖
・きび砂糖
・アスパルテーム
・異性化液糖
・果糖ブドウ糖液糖
精製された炭水化物


精製された炭水化物とは「白米、パン、麺類」などを指します。
精製された炭水化物は、ビタミンやミネラル、食物繊維を含む表皮が削りとられている「糖のカタマリ」も同然です。このような炭水化物をとると、砂糖を摂ったときと似たように血糖値が急上昇してしまうのです。
そして、がんや糖尿病のリスクやうつの発症のリスクを上げます。これには、沢山の事例報告があるので、まずは家庭の中だけでも控えるようにしましょう。
私たちができる対策
これを防ぐいちばんかんたんで効果的な方法は、「ご飯少なめ」、つまり糖質制限を始めることです。糖質制限とは、砂糖をはじめ、糖質が多く含まれる米やパン、うどん、ラーメンなどの炭水化物を積極的に減らす食生活のことです。
対策は、GI値の低い食品に置き換える方法が有効です。
- ライ麦パン
- 玄米・全粒粉のパン
- 雑穀米(もち麦や昆布を混ぜる)
これらはGI値が低く、血糖値が上がりにくいので代用品としてはピッタリなのです。
加工肉


加工肉は、体に悪影響を及ぼす添加物がふんだんに入っているため避けましょう。とくにハムやベーコン、ソーセージなどが挙げられますね。
揚げ物


揚げ物は、揚げるときに生じるAGEsという物質が体に有害です。
小麦(グルテン)


グルテンは小麦に含まれている成分であり、うどん、そうめん、冷やむぎ、餃子、パン、カレールウやホワイトソースなど、古今東西の料理で長く親しまれてきました。
しかし残念ながら、多くの人がグルテンを消化吸収できない(しにくい)体質(セリアック病、小麦不耐症)であることが判明しています。おもな副作用は以下のとおりです。
- 消化不良
- 便秘や下痢
- アレルギー反応
- 甲状腺機能を阻害する
- 脳への血流を減少させる
- ビタミンDの蓄積を激減させる
→不足すると体内のタンパク質の形が崩れて体が衰える
この事実を受け、健康意識の高い人のあいだで、小麦製品をカットするグルテンフリーが流行しました。
「食べる量を減らす」のも重要ですが、「置き換える」と考えるのも、グルテンフリーを続けるコツです。
例えば、十割そばやビーフン、フォーなど小麦粉を使わないめん類もありますし、トウモロコシ粉や米粉を使ったグルテンフリーのパスタ、うどん、ラーメン、パンなども市販されています。 また、米粉や米粉パン粉、きび粉などを買っておけば、天ぷらやフライなども今までと同様に作ることもできます。
ちなみに、グルテンをカットしていると離脱症状が起きますが、つらいのは最初の1週間~3週間程度です。しばらく我慢していると、体と頭が軽くなることを実感できる方が多いです。
完全にゼロにするのは、現代の食生活においては至難の業ですので、上手に付き合っていきましょう。
ファストフード(トランス脂肪酸)


ファストフードの多くには、たっぷりとトランス脂肪酸が含まれています。
この成分はみなさん何となくわかっているとおり、いや、それ以上にヤバイです。
なんと、総摂取カロリーのほんの1%をトランス脂肪酸に入れ替えただけでも、悪玉コレステロールの数値は激増します。2005年のハーバード論文でも摂取量が多い人ほど体内の炎症レベルが高いことがわかっており、いまやトランス脂肪酸の害に反対する専門家はいません。
また、肝臓の働きを乱すこともわかっていますので、肝臓が弱い人は特に注意して摂取する必要があります。
私たちができる対策
サラダには極力マヨネーズを使わず、良質なオリーブ油(コールドプレスのエクストラバージンオイル)かMCTオイル(中鎖脂肪酸= こちら)、レモン汁、塩、コショウで食べることをおすすめします。(これだけでもだいぶ変わります!!)
もしマヨネーズが好きな人は、自分で作るか、市販品を買う際には成分表示をよく見て「酢」「卵」「なたね油」「塩」「ハチミツ」など、ひと目で正体がわかる原材料のみで作られているものを選ぶといいでしょう。
一方で良質な脂質について代表的なものには、牧草牛から作られたバターである「グラスフェッドバター」と「ギー」があります。ギーとは、牛、水牛、ヤギなどの乳を煮詰めてろ過した調理油のことです。
ギーは加熱によって酸化劣化しづらいため料理にも利用しやすく、さらに製造段階で純粋なオイルになっているため、カゼインアレルギーや乳糖不耐症でも安心して利用できます。
カゼイン・乳糖(牛乳)


実は牛乳も体にあまりよくありません。理由は、カゼインと乳糖が含まれているからです。
カゼインには、二つの弊害があります。一つは、発がん性があること。二つめはアレルギーを起こす人が多いことです。
乳糖については、アジア人の多くが乳糖の消化に必要な酵素である「ラクターゼ」が不足しています。こういう方々は「乳糖不耐症」ともいわれており、乳糖によってさまざまな不調を抱えやすい体質なのです。
- 消化不良
- 腹部不快
- 腹痛
- 下痢
- おなら 等
また、牛乳に関していえば、「酸性食品なので、骨が弱くなる」、「飽和脂肪酸なので血液がドロドロになる」といった特徴があることも挙げられます。
基本的には控えるほうが無難ですけど、肯定的な意見も多少あります。どうしても飲みたい方は、牛乳を飲んだときの体の反応に注意を払いながら量を調節して取り入れましょう。
私たちができる対策
私たちができる対策としては二つあります。
- 乳糖の消化を助けるサプリメントを導入する
- 乳糖が少ない乳製品に切り替える
1つめは、乳糖の消化を助けるサプリメントを導入することです。このサプリを飲むことで、乳糖製品のデメリットを最小限に抑えながら摂取できます。
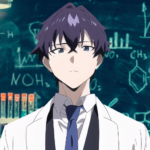
私も乳糖不耐症だが、外食にて生クリームがたっぷりのったパンケーキやスタバの甘いコーヒーなどを頂く際に頓服的に飲むことで、副作用を極限まで軽くすることに成功しているぞ!
2つめは、乳糖が少ない乳製品に切り替えることです。
ヨーグルトやチーズは、乳糖が分解されているため、牛乳よりは乳糖不耐症リスクが低いです。ただし、牛由来の乳製品で不調が出る方は代用食品を検討することが肝要です。
例えば、アーモンドミルクやココナッツミルクなどの植物由来のもの。ゴートヨーグルトやゴートチーズなどのヤギ由来のもの。これらは、牛由来のものと比べると、乳糖とカゼインいずれも圧倒的に少ないです。
ヤギ乳はまだまだメジャーではありませんけども、牧草を食べて自然な状態で育つ場合が多く、多くの汎用牛のようにホルモン剤や抗生物質のリスクもはるかに低いと考えられている安全性の高い食品といえます。
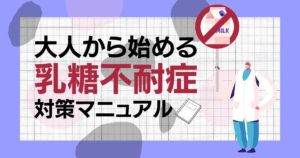
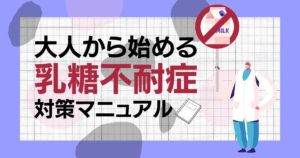
アルコール(お酒)


いわずと知れたお酒。
飲みすぎは百害あって一利なしです。
それでも飲むであれば、ワインや焼酎が比較的良いとされています。
適量は度数で変わりますが、「4%のお酒で500ml。6%のお酒で350ml」といったところです。


とはいえお酒は、「飲みにケーション」という言葉もあるくらい、コミュニケーションに役立つツールでもあるので、一概に悪者扱いすべきではないと、個人的には考えています。
そこで大事になってくるのは、日々の節酒でしょう。
普段は「4%のお酒で500ml。6%のお酒で350ml」で抑えて「毎日は飲まないこと」。そして、飲み会に行ったらしばらくはお酒を控える休肝日を作るといった切替が大事です。
もしビールを飲みたいなら発泡酒ではく生ビールにしましょう。なぜなら発泡酒は原材料が決まっていないため、添加物が大量に含まれている可能性が高いからです。
おわりに:自分の体に合うものを食べましょう


ここまでたくさんの食材を紹介してきましたが、あえて結論をひっくり返しかねないことを言ってしまうと「自分に合うものを食べましょう」ということです。
なぜなら、食べ物が合うか合わないかというのは、かなり個人差があるからです。世の中には魚が全く食べられない人や肉が食べられない人がいます。それは、遺伝子レベルで避けようとしているということなので、食べなくてもいいのです。
そういった場合は、必要な栄養素をサプリメントで摂取したり、他の食品で代替できます。
なので、本日紹介した「体に良い食品」のなかから、自分に合うモノや好きなモノを探してみて、上手に取り入れるということから始めてみてください。
そしてこれから頑張るあなたに最後の一言。
最初から100点を目指さないでください。
気にしすぎるとストレスになって本末転倒な事態になります。
70点くらいを目標に少しずつ改善していきましょう。
それでは、あなたの健康をお祈りしています。











